お金がないのはなぜ?ピンチにならないための対策と、今すぐお金を増やす方法を解説!
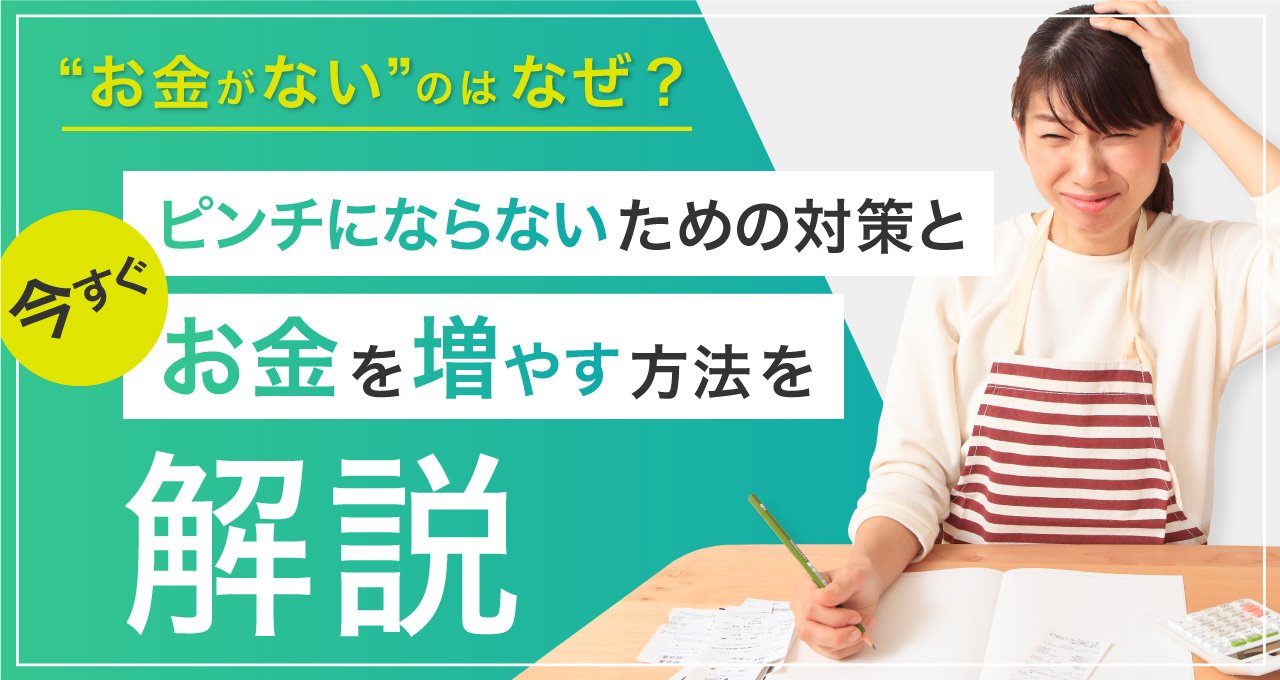
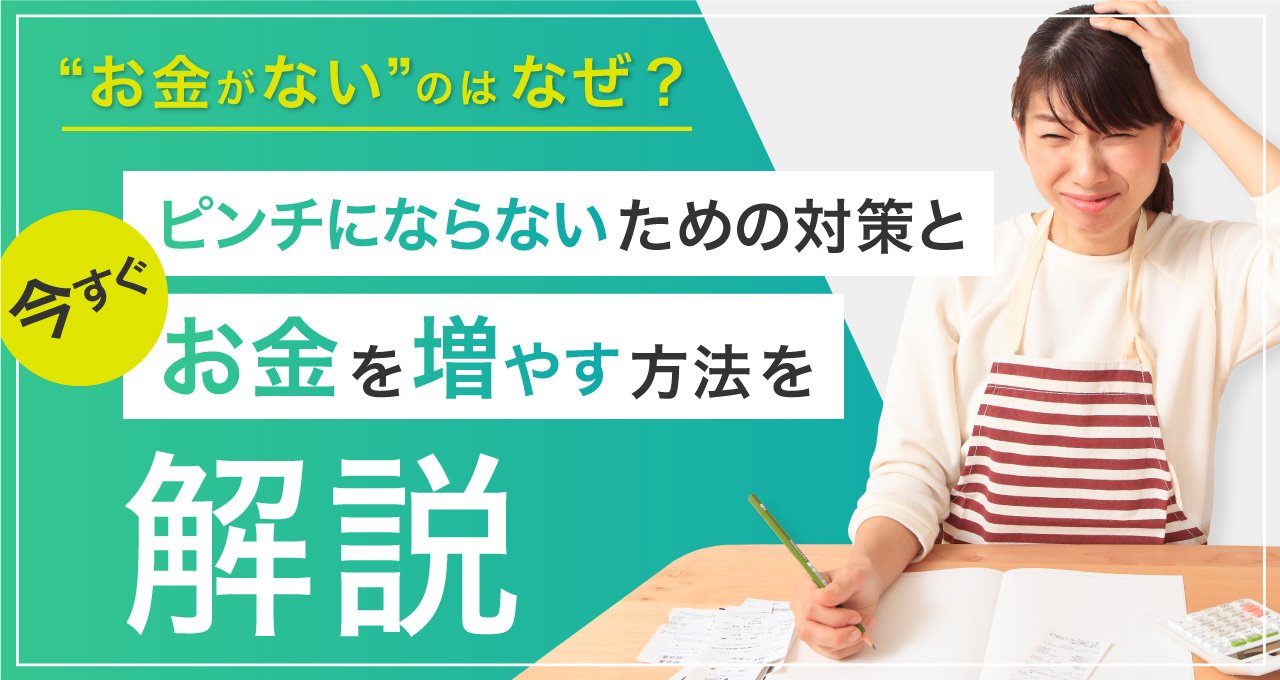
「収入はある程度あるのに、なぜかいつもお金がない…」という悩みを抱える人は少なくないのではないでしょうか。今回は、お金がない状況を避けるための中・長期的な対策や、急な出費が発生するなど、今すぐお金が必要な人のための短期的な対策などについて解説します。
なぜお金がない状況になってしまうのか?
なぜ、お金がない状況になってしまうのでしょうか?その理由は単純に「収入よりも支出の方が多い」からです。仮に貯金があったとしても「収入よりも支出の方が多い」状態が続けば、必然的に貯金は減っていきますので、最終的には手元にお金は残らないということになります。お金がない状況を解消するためには、収入を増やすか支出を減らすかのいずれかしかないということになります。
お金がない状況を避けるための「中・長期的な対策」
お金がない状況を避けるための中・長期的な対策方法にはどのようなものがあるのでしょうか。主な対策方法を確認します。
支出を把握する
お金がないという人は、給料がいくら入ったのかは把握していても、何にどれくらいお金を使っているかは把握していないという人が多いです。当たり前ですが、お金は使わなければ手元に残るはずですので、なぜお金がないのかを知るためには支出を把握することが重要となります。
支出を把握するための理想的な方法として家計簿の記帳がありますが、家計簿の記帳を続けるのが難しい人は、固定費や変動費などの大きな分類について、おお�よその支出を把握するところから始めましょう。ある程度、支出を把握することができれば、お金がない理由が「収入に対して支出が多いのか」または「必要な支出に対して収入が少ないのか」が見えてくると思います。
支出を減らす
「収入に対して支出が多い」ということであれば、支出を見直すことで改善できる場合があります。
固定費
固定費とは、月・年の単位で一定の金額がかかる支出のことになります。固定費を見直した効果は継続するため、期間が長くなるほど大きな効果が期待できます。主な固定費は以下のとおりです。
・住居費
家賃や住宅ローン、管理費、修繕積立費などが該当します。
賃貸住宅に住んでいる場合、支出に占める割合が大きい家賃を低く抑えることができれば、支出を削減する効果は大きいです。ただし、今より家賃が安い物件などへ引っ越す場合、引越し代金や敷金・礼金、仲介手数料など、さまざまな費用が発生するほか、仕事や家族に影響がある可能性もありますので、注意が必要です。
・水道光熱費
水道、電気、ガスの料金などが該当します。
電気やガスが自由化されたことで、供給会社や料金プランを自由に選択できるようになりました。現在契約されている供給会社を見直すことで、利用料金を削減できる場合があります。
・通信費
各種電話料金やインターネット回線料金などが該当します。
携帯電話料金であれば、契約プランの見直しや使用していないサービスの解約、格安SIMへの変更などによって、支出を削減できる場合があります。
・月、年会費など
例えば、利用していないジムの月会費やクレジットカードの年会費、習い事の月謝、各種サブスクリプションの利用料金などを見直すことで、支出を削減できる場合があります。
・保険料
保険の契約内容や契約継続の必要性などを見直すことで、支出を削減できる場合があります。
変動費
変動費とは、月・年の単位で変動する支出のことで、固定費以外のものを指します。
変動費の見直しは、一時的な効果はあっても継続的な効果はないものがほとんどです。また、変動費は生活スタイルなどに影響する支出も多いため、無理のない範囲で継続することがポイントとなります。主な変動費は以下のとおりです。
・食費
外食費を含めた食費を削減することで支出を削減することはできますが、無理な食費の削減はストレスにつながることから続けられなくなることも多いため、注意が必要です。
買い物の回数を少なくすることや、特売日やポイント還元が多い日などにまとめて買い物をすることで、支出を削減できる場合があります。
・日用品費
生活に必要不可欠な消耗品などに対する費用で、洗剤やトイレットペーパーなどが該当します。
食費と同様に、特売日やポイント還元が多い日などにまとめて買い物をすることで、支出を削減できる場合があります。
・交際費
友人や知人との飲食代やお土産、プレゼントにかかる費用などが該当します。
交際費は人間関係に影響する場合もある支出となりますので、金額の上限や回数に一定のルールを決めるなど、上手にやりくりするとよいでしょう。
お金を使うときの基準を決める
欲しいものをなんでも買っていると、手元にお金は残りません。お金を使うときに「今の生活に本当に必要なものなのか」「将来、本当に必要となるものなのか」などの基準を決めることで、なんとなく買ってしまうなどの無駄な出費や衝動買いを軽減することができます。
先に収入から貯蓄分を差し引く
先に収入から貯蓄分を差し引き、残ったお金でやりくりするという方法です。生活費などを使った後に残った分を貯蓄するというのが一般的な考え方ですが、お金がないという人は、貯蓄に回すお金が残っていないことも少なくありません。この方法であれば、確実にお金を貯めることができますので、お金がないという問題からは解放されます。
貯蓄に回したお金を使ってしまうのではないかと心配な人は、貯蓄に回す金額を少額からスタートし、引き出しにくい定期預金や積立預金、つみたてNISA、会社の財形制度などを活用するとよいでしょう。
収入を増やす
「必要な支出に対して収入が少ない」ということであれば、収入を増やすことで改善できる場合があります。
・本業で収入を増やす
スキルアップや成果を出すなどによって、本業で収入を増やします。
・転職で収入を増やす
本業での昇給が望めないなど場合は、転職をすることで収入を増やします。
・副業で収入を増やす
副業が認められている��場合は、副業をすることで収入を増やします。
今すぐお金が必要な方のための「短期的な対策」
今すぐお金が必要な場合など、短期的な対策方法にはどのようなものがあるのでしょうか。主な対策方法を確認します。
不用品を売却する
リサイクルショップやフリマアプリなどで不用品を売却する方法です。比較的手間や時間も少なくお金を得ることができる方法ですが、需要の高いブランド品などでなければ、あまり高額な買い取りは期待できません。
国や自治体などの支援制度を利用する
各制度の給付要件を満たすことで、国や自治体などの支援制度を利用できる場合があります。また、年金や税金の支払いが猶予される制度もありますので、国や自治体に確認してみましょう。
短期のアルバイトをする
短期のアルバイトで収入を得る方法です。即日払いのアルバイトをすることで、働いた日に給料を受け取ることができます。なお、企業によってはアルバイトを認めていない場合もありますので、注意が必要です。
お金を借りる
親族・友人などの個人や金融機関からお金を借りるという方法です。カードローンやクレジットカードに付帯するキャッシングサービスを利用することで、即日融資が受けられる場合もあります。
また、質屋に一時的に品物(アクセサリーやカバンなど)を預け融資を受けるという選択肢もあります。質屋は、担保となる品物を預けてその品物の価�値に見合った額の融資を受けるものであり、品物を返却してもらうためには、借りたお金と定められた利息を返済する必要があります。
金融機関からお金を借りる際の注意点
金融機関からお金を借りる際の主な注意点について確認します。
・返済義務が発生する
期日までに返済するという義務が発生します。
・利息の支払いが発生する
借りたお金に加えて利息を支払わなければなりません。
・借りることができるお金は無限ではない
金融機関によって異なりますが、一般的には申込者ごとに借入限度額を設定しています。また、貸金業者からお金を借りる場合は総量規制(※1)が適用されます。
総量規制
総量規制とは、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、貸金業者から借りられるお金の総額に制限を設ける貸金業法の規制のことで、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入はできなくなります。なお、銀行は貸金業者に該当しないため、銀行からの借入に関しては総量規制の対象外となります。
(例)利用者の年収が300万円の場合、貸金業者から100万円までしか借りられないということになります。
お金を返すことは大変です。お金を借りてまで必要なものなのかを検討し、借入金額は極力減らすようにすることが望ましいです。
【タイプ別】お金がないときの借入先
一般的な借入先をタイプ別に確認します。
時間に余裕がある&低金利で借りたいなら「フリーローン」
主に銀行が取り扱う、使いみちが自由なローンを指しますが、事業資金や投資資金などとしては利用できません。一般的に借入可能回数は1回までとなっており、キャッシングやカードローンと比較すると金利は低く設定されている傾向にあります。また、融資されるまでには一定の時間がかかるため、即日融資には対応していません。
即日融資も可能な「カードローン」
主に消費者金融が取り扱う、使いみちが自由なローンを指します。一般的にフリーローンと比較すると金利は高めに設定されている傾向にありますが、カードを利用してATMですぐに現金を引き出せるなど、利便性は高いです。また、大手や複数の都道府県に店舗がある中規模の消費者金融が取り扱うカードローンであれば、即日融資に対応している場合が多いです。
緊急&少額の場合は「クレジットカード付帯のキャッシングサービス」
クレジットカードを利用して、ATMなどから現金を借りることができるサービスです。フリーローンやカードローンと比較すると金利は高めに設定されている傾向にありますので、利用には注意が必要です。
お金がないときにしてはいけない対処法
お金がないときにしてはいけない対処法には、どのようなものがあるのでしょうか。主なものを確認します。
家賃を滞納する
家賃を滞納することで、その月の生活費は確保できるかもしれませんが、家賃は毎月の支出の中でも大きな割合を占めていることが多く、滞納分の支払いは翌月以降の支出にも大きく影響することになります。また、家賃の滞納が続くと、下記のようなことが起こる可能性もあります。お金がないときの対処法として家賃の滞納は避けるようにしましょう。
・連帯保証人に連絡が入る
物件の契約者から滞納分の回収が難しい場合は、��連帯保証人に連絡が入る可能性があります。家賃を滞納していることが連帯保証人に伝わるだけでなく、連帯保証人に滞納分の支払いを求める場合もありますので、結果として連帯保証人へ迷惑をかけてしまうことになります。
・強制退去させられる
家賃の滞納が続くと、最終的には賃貸借契約が解除され、物件から強制的に退去させられる可能性があります。なお、強制退去となっても、滞納分の家賃の返済義務が免除となるわけではなく、強制退去にかかった費用を請求される場合もあります。
・信用情報機関に履歴が残る
賃貸借契約で保証会社(家賃保証)を利用した場合、家賃を滞納するとその内容が信用情報機関(※1)に登録され、履歴として残る可能性があります。各種ローンやクレジットカードなどの審査において、信用情報機関に登��録されている情報は重視されるため、家賃を滞納した情報が信用情報機関に登録されることで、各種ローンやクレジットカードなどの審査に通らない、分割払いが利用できなくなるなどの可能性があります。
また、クレジットカードで家賃を支払っていた場合も同様に、クレジットカードの支払い口座から家賃の引き落としができなかった情報が、信用情報機関に登録される可能性があります。
※1 信用情報機関
消費者の信用情報を管理し、加盟会員企業から与信の目的の照会に応じて、個人信用情報を提供する金融庁指定の機関です。日本で個人の信用情報を管理している信用情報機関は「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つです。
・遅延�損害金が請求される
家賃を滞納した場合、滞納した期間に応じて発生する遅延損害金を請求される可能性があります。
【遅延損害金の計算式】
借入残高(家賃)×遅延損害金の利率÷365日(うるう年の場合は366日)×滞納日数
(遅延損害金の利率の上限は14.6%)
クレジットカードの現金化
主にクレジットカードのショッピング枠を利用して商品を購入し、その商品を売却して現金を受け取る方法です。クレジットカードの現金化で一時的に現金を用意するこ��とはできますが、一般的に換金率は低く、クレジットカード会社への債務も残ります。また、クレジットカード会社の利用規約で現金化目的での利用を禁止していることも多く、規約違反をすればペナルティーなどを受けることになります。
個人間融資の利用
個人間融資では、主に個人を装った闇金(ヤミ金)業者などが、SNSやインターネット掲示板などを利用して融資を勧誘することが多く、違法な高金利での融資や個人情報が悪用されるなど、犯罪被害やトラブルなどに巻き込まれる危険性があります。
お金がないときは24時間・即日借入OKの「LINEポケットマネー」を検討※
スマホアプリから申込・借入ができるサービスは増えつつありますが、日頃からLINEアプリを使っている人であれば、LINEアプリから操作&申込ができる「LINEポケットマネー」を利用することができます。「LINEポケットマネー」なら、24時間利用可能(※2)で、即日融資を受けることができます(※3)。
※ メンテナンス等の時間帯を除きます
※ 借入額や条件、申込時の混雑状況などにより即日融資が難しい場合もあります
まとめ
支出の把握やお金を使うときの基準を決めるなど、支出の見直しを無理のない範囲で継続することで、お金がない状況を解消できる場合があります。また、今すぐお金が必要な場合は、即日融資に対応しているカードローンやクレジットカード付帯のキャッシングサービスなどを利用するという選択肢もあります。
日頃からLINEアプリを使っている人であ��れば、身近なLINEアプリで利用できる「LINEポケットマネー」の利用を検討するのもよいかもしれません。
執筆者
中田 真
給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンでしたが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。現在、生活に身近なお金・終活・老後の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。

